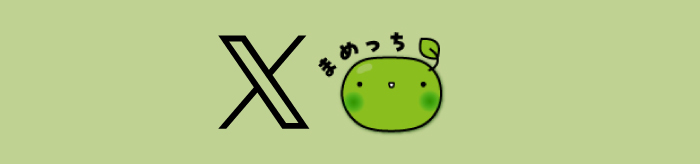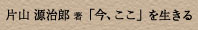鮒寿司(滋賀県)

鮒寿司は、塩漬けした魚と米を一緒に漬け込み、自然の力でじっくり発酵させた「熟れずし」の一つで、奈良時代頃から伝わる発酵食品です。この発酵技術は中国や東南アジアでも古くから使われ、魚を長期保存できるようにする知恵として伝えられてきました。
滋賀県では琵琶湖で獲れるニゴロブナを中心に、ウグイ、アユ、ハス、コイなどの様々な淡水魚を使った熟れずしが作られており、中でも「鮒寿司」は最も代表的な存在です。神社の祭礼において神に捧げられるほど、地元の食文化に根づいています。
特に珍重されるのが春先の子持ちニゴロブナ。塩漬けし、ごはんと一緒に漬け込むことで乳酸発酵が進み、骨までやわらかく、そして卵のプチプチとした食感を楽しみながら食べられるようになります。また乳酸菌が豊富なことで整腸作用もあり、滋賀県では体調を崩したときに薬代わりに食べる習慣があるほど、長年にわたり人々の健康を支えてきました。
鮒寿司の歴史
鮒寿司がいつ誕生したかは明確ではありませんが、平安時代の文献には「近江国筑摩厨(現在の滋賀県米原市)から鮒ずしが朝廷に献上された」との記録が残っており、少なくとも1200年以上の奈良時代の頃から歴史があると考えられています。
鮒寿司(滋賀県)の豆知識
- 鮒寿司の食べ方は?
そのまま薄切りでいただくほか、酢飯と軽く和える、お茶漬けにする、クリームチーズと合わせるなどで酸味と香りがまろやかになります。 - 保存と食べ頃は?
乾燥しやすいので、切り口をラップで密着させて密閉容器に入れ冷蔵保存します。食べる分だけ薄く切り出すのがコツ。香りが強いと感じる場合は、切ってから数分置くと酸味が落ち着きます。長期保存は風味が変わるため避けて、早めに食べ切りましょう。
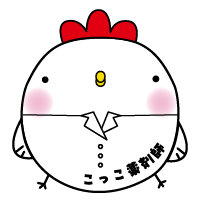 薬剤師の食育コメント
薬剤師の食育コメント
鮒寿司に多く含まれる乳酸菌には、腸内環境を整え、発汗を促す働きがあります。さらにビタミンB1、各種ミネラル、天然の抗菌成分も含まれており、体調を崩したときの回復食として非常に優れています。保存食というだけでなく、滋養強壮や美容にも良いと言われ、健康食品としても注目されています。

鮒寿司の作り方

 材料|仕込み用(1尾分)
材料|仕込み用(1尾分)
- ニゴロブナ(またはフナ)・・・1尾(卵を持ったものが理想)
- 粗塩・・・適量(魚の重量の20~30%)
- 炊いたごはん・・・適量(魚が包める量)
- 重石・・・適当な重さのもの
- 殺菌済みの保存容器(密閉できるもの)
 調理ステップ
調理ステップ
- フナの内臓とエラ、ウロコを丁寧に取り除き、血合いを水で洗い流して、しっかり水気をふき取ります。
- 魚の身全体に粗塩をすり込み、塩が全体に行き渡るようにします。エラにも塩を詰め込みます。
- 密閉容器に魚を並べて、落とし蓋をした上から重石をし、冷暗所で2〜3週間置きます(塩漬けの工程)。
- 塩漬け後、魚を取り出して塩を洗い流し、再度水気をよくふき取ります。約1日程陰干しをします。
- 炊きたてのごはんを冷まし、魚全体を包み込むように漬け込みます。(消毒など清潔なもので魚に触れてください)
- 再び密閉容器に詰めて重石をし、冷暗所で2〜3か月発酵させます。
- 発酵が進んだら食べごろ。薄切りにしてそのまま、またはお茶漬けなどでいただきます。(好みに合わせてごはんは取り除いてください)
※本格的な鮒寿司は発酵の管理が難しいため、初心者は市販品から味を学ぶのもおすすめです。
※衛生面には十分注意し、信頼できる魚を使用してください。
※乳酸発酵食品なので、容器に入れたままだと約3年程保存ができます。