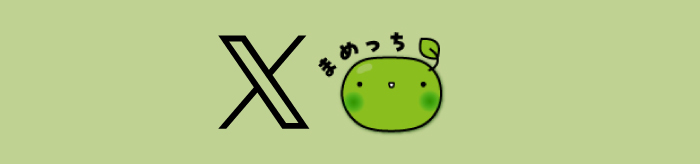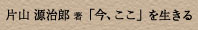柿の葉寿司(奈良県)

柿の葉寿司は、奈良県を中心に近畿地方で古くから親しまれてきた押し寿司の一種です。塩でしめた鯖や鮭を酢飯にのせ、香りの良い柿の葉でひとつずつ丁寧に包み、重石をかけてなじませます。防腐効果のある柿の葉に包むことで保存性を高め、冷蔵技術のなかった時代に山間地で海の幸を楽しめる工夫として発展しました。今では地域の名物として、土産物や贈答品としても親しまれています。
柿の葉寿司の歴史
柿の葉寿司の歴史は江戸時代中期にさかのぼるといわれています。奈良県南部では、海が遠く新鮮な魚を手に入れるのが困難なため、塩漬けにした鯖を酢飯にのせ、柿の葉で包んで保存する方法が広まりました。夏祭りやお盆などの人が集まる行事では、家族総出で柿の葉寿司を仕込み、客人にもてなすのが習わしとなっていました。現在でも、伝統を守りながら多様な具材や製法が登場し、進化を続けています。
柿の葉寿司(奈良県)の豆知識
- どんな魚が使われる?
昔から使われてきたのは塩鯖ですが、近年では鮭・鯛・穴子なども人気。季節や地域、好みによって使い分けられています。 - 柿の葉にはどんな効果が?
柿の葉に含まれるタンニンやポリフェノールには抗菌作用があり、食材の鮮度を保ちやすくします。また葉の香りも柿の葉寿司の風味の一部です。 - 保存方法と食べ頃は?
包んでから1〜2日ほど常温の涼しい場所に置くと、酢飯と魚、柿の葉の風味が調和します。冷蔵庫に入れる場合は、乾燥しないよう密閉容器で保存します。 - 奈良の郷土文化との関係
柿の葉寿司はお盆や祭りのごちそうとして親しまれてきました。地域によっては「家ごとに味が違う」といわれ、家庭の味として代々受け継がれています。
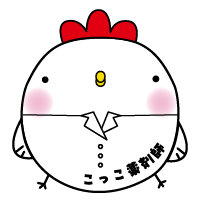
薬剤師の食育コメント
柿の葉寿司は、魚の良質なたんぱく質と酢飯の糖質、さらに柿の葉の抗酸化成分を一度に摂れる伝統食です。整腸作用が期待できる酢や、青魚のDHA・EPAなど、現代の健康志向にも合ったバランスの取れた一品といえます。保存性も高いため、防災食や保存食の知恵としても注目されています。

柿の葉寿司の作り方


材料|2人前
- 【材料】
- 酢飯・・・2合分
- 塩鯖(または鮭など)・・・6切れ
- 柿の葉・・・6枚(きれいに洗い、水気を拭き取っておく)

調理ステップ
- 酢飯を一口大に握り、塩鯖をのせる。
- 柿の葉の表を下にして酢飯ごと包む。
- 清潔な容器に並べ、上から軽く重しをのせて一晩寝かせる。
- 翌日から食べ頃。2〜3日以内に食べきる。

酢飯の作り方(基本の割合)
- 米2合(炊きあがり約600g)
- 酢・・・60ml
- 砂糖・・・30g
- 塩・・・5g
※小鍋で軽く温めて混ぜ合わせ、炊きたてのごはんに回しかけて切るように混ぜます。