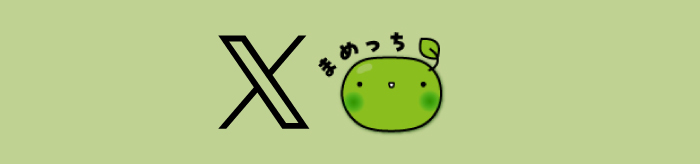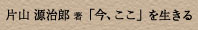金山寺味噌(和歌山)

和歌山県を代表する発酵食品「金山寺味噌」は、食べる味噌として知られています。
大豆と麦、米などに、刻んだナスやウリ、生姜などの野菜を加え、麹の力でじっくりと熟成発酵させます。調味料というよりもおかずとしてそのまま食べることができ、酒の肴やご飯のお供に最適です。
具材感と優しい甘さ、芳醇な香りが特徴で、まろやかな旨味は発酵ならではのものです。現在では全国に広まりつつありますが、和歌山では昔から家庭の常備菜として親しまれ、夏の贈り物などにも重宝されています。
金山寺味噌の歴史
金山寺味噌の起源は鎌倉時代にさかのぼります。高僧である覚心が、修行先である宋(中国)の径山寺から持ち帰った味噌作りの技術が紀州(現在の和歌山)に広まったのが始まりとされます。紀州・由良の興国寺の門前で作られ「金山寺味噌」と呼ばれるようになりました。
金山寺味噌(和歌山県)の豆知識
- 金山寺味噌の特徴は?
食材としてナス、ウリ、生姜、シソの実などが使われ、麹と一緒に発酵することで食感や風味が豊かになります。白味噌に近い甘みと、具材の旨みが重なり合った独特の風味が魅力です。 - 和歌山以外では?
千葉県や静岡県などにも金山寺味噌は伝わっていますが、和歌山のものは特に入っている野菜の種類が多く、甘みが強くて具沢山なのが特徴です。 - 金山寺味噌の食べ方は?
そのまま食べるだけでなく、冷ややっこやきゅうりに添えたり、焼きおにぎりの具にするなど、さまざまなアレンジが可能です。
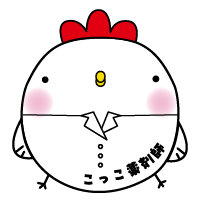
薬剤師の食育コメント
金山寺味噌は、発酵過程で生まれる酵素や乳酸菌を含み、整腸作用や免疫力の向上が期待されます。大豆由来のたんぱく質に加え、野菜のビタミンやミネラルも摂れる、理想的な発酵食品です。

金山寺味噌の作り方


材料|作りやすい分量
- 米こうじ・・・500g
- 麦こうじ・・・500g
- 大豆・・・500g
- なす・・・2本
- うり・・・1/2本
- 生姜・・・30g
- 塩・・・100g
- 砂糖・・・150g

調理ステップ
- 大豆を一晩水に浸し、やわらかく煮てつぶします。
- なす、うり、生姜はみじん切りにして軽く塩を振り、水気を出します。
- 米こうじ・麦こうじをほぐして、塩・砂糖とよく混ぜ合わせます。
- すべての材料をよく混ぜ、清潔な容器に詰めて空気を抜き、密封します。
- 冷暗所で1〜2ヶ月ほど発酵・熟成させて完成です。